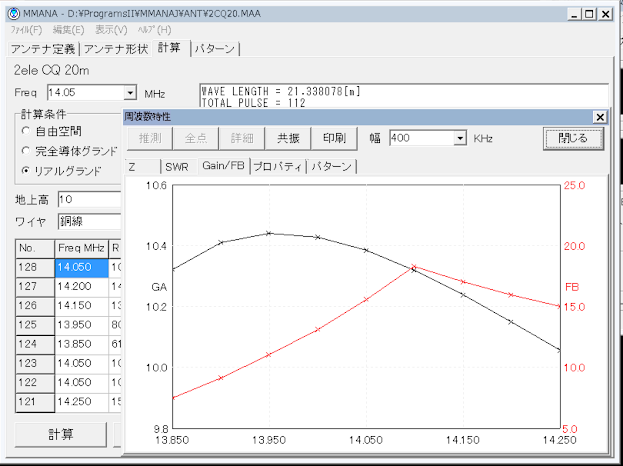FM送受信機(トランシーバ)製作失敗の反省文
1 FM受信機
(1)スーパーヘテロダイン式FM受信機
図1. FM検波/復調回路の過渡解析結果 (LTspice(Linear Technology社開発)を利用しパソコンで計算。) 
(送信機から和音3重音を送信し、復調した和音の電気信号波形を見たところ)
シングルスーパーヘテロダイン式受信機の仕様
・VFO : 130MHz台 1TR LC共振発振回路[※1]
・受信周波数:145.00 MHz(コールチャンネル)、145.08MHz の2ch.[※2-1]
・OSC: 12MHz帯TR水晶発振器の12逓倍型 [※2-2]
・LNA: 3SK22[※3] x1
・Mixer: 2SC454 x1 ベース信号注入型 [※4]
・IFアンプ:10.7MHz 東芝IFアンプIC 7061P[※5] x2
・FM検波方式:レシオ検波(東光社10.7MHzディスクリミネータコイル使用)
・AFアンプ:NEC uPC20C[※6] 最大1W スピーカ駆動
・スケルチ回路:uPC20CのMute端子をアサート/ネゲート
現象:スーパーヘテロダイン式FM受信機を製作した。アンテナを接続し、電源オン後、144.08MHzを受信すると、近傍周波数の複数のFMチャネル通信が混信してしまう。
原因:「ラジオの製作」の製作記事では、セラミックフィルタ1個 10.7MHzの実装を指定していた。これはFM放送用帯域幅仕様でFMチャネル通過フィルタ帯域幅が広く、アマチュア無線144MHz帯 チャネル帯域幅20KHzよりずっと広すぎたため。
対策:不能。(基本設計からやり直しが必要となった。) 製作当時、水晶フィルタによる帯域エッジのキレの良いFM用高性能フィルタがあったが、高価で購入できなかった。(トランシーバ部品価格=数千円の数倍の価格) FM用水晶フィルタは部品サイズが大きく、製作済みの基板サイズ制約から実装できなかった。セラミックフィルタは安価だが、20KHz帯域幅に合う市販品はなかった。
145.08MHzの周波数は、3逓倍すると435.25MHzのATV(NTSC式テレビ)に対応できるので選定したが、実験途中にバンドプランの変更があり、1200MHz へATV帯が移動してしまった。
[※1] LC共振自励式VFOは、発振周波数が高いほど周波数安定度が悪くなる特性が見られる。市販のFMラジオではAFC制御で同調ずれを補正していた。FETのほうがTRより発振周波数が安定すると読んだ記憶がある。この説が正しいかどうか根拠は不明。本構成回路にはAFC回路がないので、時間的に受信局への同調がずれる現象が発生した。
[※2]こうしたVFO周波数が安定しない課題を、水晶発振器の周波数安定特性を使い解決しようとした考え方が読み取れる。水晶が144-145MHzのような高い周波数を直接発振できない課題を、逓倍回路で解決している。しかし、この逓倍により発生する高調波を減衰させるフィルタ性能が十分といえる工夫が見られない。
[※3]当時のデュアルゲートMOS FETの先端デバイスと思われる。これをRF段や、MIXER段、IF段に使用すると、高感度と混変調特性の改善が両立されると大きな広告が見られる。これは事実かどうか不明。
現在の通信機ではむしろRF段LNAは、大変高い周波数まで使えるBJT TRやICへ移行している。デュアルゲトートMOS FETはいつの間にか姿を見なくなった。IF段はICアンプへ、さらに受信機全体をワンチップICへ、最近ではデジタルIC製品も多種類出てきている。
メーカ側ではIC設計化、デジタル化信号処理の方向で進んでいるが、メーカ技術のノウハウが教育や書籍へフィードバックされず、設計内容がブラック・ボックス化し見えず、設計文化のギャップ拡大が見られる。
[※4] 書籍(1976年発行)の設計法では、TR一石でミキサー回路で構成している。しかし、書籍現本回路を再確認したところ、設計概念の根底に、ミキサー回路にはアナログ乗算機能が必要であることの理解の痕跡が見られない。(1968年がギルバート乗算器発明だから、これは周波数変換原理への理解が無い未熟な設計文化状況が存在していたと思われる。) 単に、一石のTRのベースに、受信RF信号とOSC信号が入力されており、これは加算回路なので乗算である周波数変換は不能になってしまう。OSC出力をC結合でエミッタへ接続する改造により、TRのスイッチング動作で、周波数変換動作をするように自分で考え改良した。[※b]
[※b]ごく近年の新刊:トランジスタ技術2015年1月号、情熱のFMラジオにも、TRスイッチンング動作式Mixer回路例がある。書籍の技術レベルは著者に依存し、こうした1970年代レベルの旧式設計から未だに21世紀を15年も過ぎても進歩の見られない回路採用が繰り返し掲載され続けている。これは、電子工学の学問や技術進歩が見られない、技術発展停止状態の印象を受けた。
近年の読者側の興味は小型マイコンボード/初歩のioTにあるが、アナログ回路は理解されにくいので、こうした入門者レベルに合わせないと書籍が売れない事情があるのかもしれない。
これは、おそらく素人より若干優秀なプロの記事が載るので、読者側では、進歩的業界の技術水準や技術動向がわからなくなってしまうのではあるまいか。世間では、日本の家電は世界一と未だに言う人を良く聞くが、海外のSNSを見ると海外在住日系人から見ても日本製家電の魅力は無いという見方が聞かれる。一方、アジア大陸生産の家電デジタル家電は安価だが、品質上の大きな課題、全く動作しない偽物の流通があることも聞かれる。そうした状況なので、努力のやりがいはあるかも。
2 FM送信機:
図2. FMワイヤレスマイクの変調動作の過渡解析オリジナル (2004年に発表したオリジナルの初期実験)
歪んではいますがひょっとして日本初の試みか? ネットで話題になりました。この回路図は、コイルの結合定数の指定が漏れています。L=L1+L2+M*√(L1*L2) こんなインダクタンス式だったと思います。
M=0.9くらいがモデルとして良い値です。
2.1 FMワイヤレスマイク
1200円で通信販売で購入した2石FMワイヤレスマイクを製作した。
現象:FMラジオ(ラジカセ)に電波が受信できない。コイルの巻き数、幅を変化させたが、どうしても電波が受信できない。
原因:平ラグ板の一箇所のはんだづけ配線が漏れていた。
対策の経緯:先生(家の近くの工業高校電気課の先生)が、ワイヤクリップケーブルで、その端子をショートすると、FMラジオからポワ〜ンとハウリング音が聞こえた。
先生がFMラジオの選局ダイヤルを回して、
「電波の子供(スプリアスのこと)が他にあるから、まだ調整が必要だね。」
と教えてくれた。これは、FMワイヤレスマイクのおそらくキット製品にもともとあった設計不良で、バイアス電圧が適切でないために、異常発振を起こしていた、と推定されるが、その現象を僕も先生も見抜けなかった。
この時代は、先生の給料でもオシロスコープは買えない。僕ら子供らは当然持ってないし、学校にある高価なものでも、76MHz〜90MHzのような高い周波数の電波を測定できるオシロスコープはない。世界にもあったかどうか。使えるのはテスター程度の全盲状態のような手探りと試行錯誤のエンジニアリング開拓期か。
・FMコイル幅を変化させたが、発振周波数を単一のものにすることはできなかった。
・コイルの巻き数や並列コンデンサの容量を変えたが、状態を改善できなかった。
・アンテナ線を、コイルタップにつけると、周波数が不安定に変化し、ラジオの同調から外れてしまうことに気づいた。
・コイルのタップ位置をずらしてアンテナ線をつけてみた。コイル巻線の1回巻き毎、全周についてタップ引き出しを試した。
アンテナの長さは78MHzに対する1/4λ=96cmのビニルリード線をつけた。長さを長くして、遠くに電波を飛ばそうと試みたが、失敗し、電波の伝達距離は5m程度が限界だった。
図3. バリキャップ式FM変調回路の過渡解析(FM変調波の品質が図2.よりずっと良い。)
このような測定器も、理論もない状況では、「試行錯誤法による解決法」がとられ、原因不明のまま、動作する回路の動作パターンを探した。[※a]
[※a]先進国では半導体・トランジスタ等価回路、発振理論などが科学者により理論構築がされていた古くからの歴史記録を見るが、国内には、そうした電気・電子・制御等、自然科学分野で、理論構築の研究記録や文献があまり見ない。見るのは八木宇多アンテナ、長岡半太郎さんのコイル(ソレノイド)の長岡係数、真空管ラジオの写真くらいで研究実績が非常に少ない感じ。おそらく日本は、江戸時代の鎖国以降、戦後になってようやく海外の電気工学、電子工学の書籍、文化の輸入が始まったらしい。
日本は文化の出発が既に出遅れ先進国に劣勢をとっていた。バブル景気の幻影の後、日本の真の実力の姿が見えてきたのかもしれない。技術の遅れは依然として解消されていないが、テレビでは何度も全く同じ古い昔の成功談を繰り返す放送が多い。こうした話を何度も聞いていると普通の人は耳にタコができていても気づかなくなる。
現在では、自動車用に交通取り締まりレーダー、気象降雨レーダが使われ、僕らもHRO FFT観測、干渉計を実験するまでになったが、僕らも所詮は、その程度。非力なんだと思う。
2.2「CQ Ham Radio誌」掲載 のハンディー型12逓倍式FM送信機
(1)現象:マイクへしゃべっても、音声がFM受信機から聞こえない。無変調状態となる。
(2)原因:記事の設計ミスというより、結果的にけして再現できない回路方式エラーによる記事だったことがわかった。(設計ミスで動作確認されていない回路が、そのまま書籍に載った。最近になってようやく「再現性」という言葉が使われ、その大切さが認識されるようになった。)
12MHz無調整型水晶発信機TRのエミッタ端子へ、1〜2石低周波アンプを接続した設計だったが、水晶発信器が固定した安定した周波数を発振する特性であるため、周波数偏移が全く発生せず無変調となった。(事実と異なる、再現性の無い記事が頻繁に専門的な書籍に良く載っていたが、僕ら一般の読者は、そのままそれらを本物と信じた。)
(3)対策:水晶発振回路を、リアクタンス管ベクトル合成位相変調回路(「ラジオの製作誌 50MHz FMトランシーバ」)に変更。バリキャップ容量を変化させることでLC発振周波数を変化させ、さらに12逓倍で、十分な周波数または位相変異を得るもの。対策後、FM受信機から音声が聞こえるようになった。(この記事は本物だった。)
(3)現象:1WのFM送信実験中、自宅UHFテレビに高調波による受信障害が発生した。ダミーロード50Ω (20W耐電力)を使用していたので、ビデオケース(シールド用小型鉄製ケース)をかぶせていないコイルから輻射される高調波がUHFチャネルと重なってしまったと思われる。
対策:不能。家族からのテレビ受信障害の苦情で、ただちに実験中止。
(4) PLL対応への遅れ
水晶発振チャネル式が主流の時代があり、水晶が大変高価であったため、144MHz全周波数帯のチャネル装備ができない人が多かったと聞いた。LC自励式VFOは、発振周波数が高くなるほど、周波数安定性がない特性が知られていて、144MHz VFOへの直接FM変調方式は使われていなかったと思う。低めの周波数のVFOをアップ・コンバージョンするプリミックス方式はあったかもしれない。
その後直ぐ、無線機メーカは、水晶チャネル逓倍式FM変調から、PLL VCOにFM変調をかける方式に移行した。
(課題:PLLは周波数また位相変動をキャンセルするように自動制御するので、VCO制御の時定数を遅くしないと、音声入力による周波数変化に追従して周波数変化が起こらなくなる。)
PLLはデジタル・マイコンでのデジタル式周波数制御に向いているため、デジタル技術を持つメーカがアナログ技術しか持たないメーカを次第に圧倒するようになっていた。
米国でCB無線が大流行し、その工場ゴミのPLLモジュールが、秋葉原で300円〜400円で買えた時期があった。メーカのPLL対応の流れに対抗し、FM変調送受信機も計画したが、実験途中で学校を卒業。
大学時代、学業は著しく思考負荷が重く、成績評価を得るのが厳しかったものの、比較的平和な心の安心感があった。就職・社会人になると、それどころではない地獄に突入した。巨人の星を信じていたのは人生戦略上の最大の誤りだったと、大変残念に思い、反省している。こうした精神論万能と超人的努力ですべてが実現可能と考える思想は、現代でも社会的文化構造に暗い影を落としたまま、大きな負の歪を生じさせたまま、改善されていないと心配するものです。
A. 時代とFM技術の推移
144MHzモービル無線(車載トランシーバ)花盛りの記事が1970後半の書籍に記載があり、430MHz運用はメーカ製品が無い、周波数が高く難しいと書いてある。水晶発振チャネル式が主流で、水晶が大変高価であったため、144MHz全周波数帯のチャネル装備ができない人が多かったと先輩から聞いた。TS-700も高価で、買える人は少なかった。水晶チャネルはオプションだったと思う。
空前の大BCLビームで、家電各社から10kHz機械式周波数読み取り短波受信ラジオがバカ売れした。しかし、その技術は未熟で、通信機メーカは既に1KHz周波数読み取りを実現済み。技術的に家電メーカの持たない潜在力を持っていたことがわかった。
その後、ラジカセがバカ売れする時代に入り、日本の家電は世界一と勘違いされる時代が来たのだと思う。その後、遅からずして、無線機メーカは、水晶チャネル逓倍式FM変調から、PLL VCOにFM変調をかける方式に移行した。
その後、430MHzハンディFMトランシーバがメーカから発売され、アマチュア無線人気は50MHzから430MHz FMへ移っていき、430MHz FMは入門バンドになり、土日は山岳移動運用が流行った。144,430は、朝、夕は、若い奥様が旦那様を呼び出す声が大変多く聞かれた。その後、一般市民用に、自動車移動電話が発売されたが、高価で普及はあまりしなかった。黒塗りの車の後部にオレンジ色キャップの黒いホイップアンテナが見られた。
ポケットベルの後、携帯電話が流行りだすと、無線機からは、若奥様方の声が聞かれなくなっていった。旦那さんを呼び出す奥様方は、携帯電話利用へ移行したと思われる。
1997年ごろカナダの携帯電話機会社 ノキア社で革命的発明があった。複素数信号処理による変復調方式の国際特許が取られた。時代は急激にSDR、デジタル通信へ進んだ。海外ではこうしたSDRラジオを熱心に研究する人々の情報交換が見られるが、日本では、ほとんどそうした動きが見られない。無線機には数値演算式変調方式と書かれたが、その方式はわからず、中身がブラックボックス化し、機密化していた。[※1]
現在では、小学生や中学生、高校生まで、スーマートフォン、携帯電話で、無資格・無免許でも、誰でも、そうした数値演算変調方式の無線通信ができるように表面的には恵まれた社会になった。しかし、買って使うだけという、全般的な文化低下の印象があり、インターネットには、大学の先生にも、必要水準に到達できていない講座や、大学生でも進歩性を感じない質問と回答が目立つように感じる。 スマホを使うと頭が悪くなるのは本当なのだろうか。
日本では、このスマホ普及の影響により、顧客層の主流が流れ、アマチュア無線局の局数が減少している。ところが、米国では逆に増加している。これは、社会に貢献する人材育成の考え方・国家戦略の差が表れている現象かもしれない。
[※1]: 僕は、そのブラックボックスと同機能の設計技術を、全くの空白状態から、独自に構築する努力をしています。長らく職人気質と聞く従来のハードウェア設計文化への違和感と、長期の誤認識設計結果の存在を見てからは、設計という学問の概念がそっくり抜け落ちているような疑問を感じました。こうした課題認識の元で、ソフトウェア設計で見られる従来からのトップダウン設計、段階的詳細化、構造化設計、物理・数学の概念を加えることにより、従来の課題が認識できない状態から、明確な課題を確実に短期に解決できる新しい設計文化構築、陳腐化し時代に合わなくなった、古すぎて使えない職人気質文化からの脱却ができたら、と願っています。