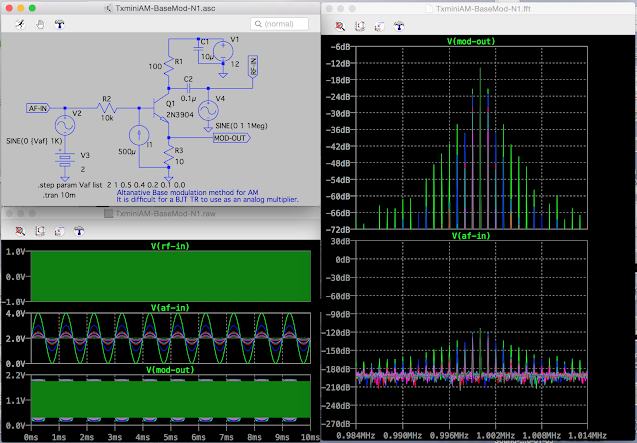課題:
設計過程:
(1)LTspiceでJFET, NチャネルMOSFETを選択するとそれらの一覧表が表示される
しかし、多数の知らない名前のFETばかりで、
このため、FETを使用する回路設計が先に進めない。
技術的課題:
(2)Vth(バイアス電圧)
(3)JFETを選択、
原因:
・どのFETがどの周波数まで、
・FETのVth(ゲートバイアス電圧)は、
・JFETはVgs=
Vgs=0VまたはVgs≒
・MOSFET N-channel は、Vgs >0 正電圧にバイアス電圧をとるが、このVthに達していないと、
利得はマイナスになる。(AC解析をすると、
0. FET選択の選択/判別のノウハウ:
次の基準を目安にLTspiceのFET選択画面から使えそうな小信号用FETを選ぶ。
・Rds(ドレイン-ソース間ON抵抗)
・Rdsが数mΩと小さいものは、大電流スイッチング用である。
・Rdsが大きいほど利得は40dB程度と、
・周波数が高くても使えるFETは、
1. DC解析によるデバイス特性の把握手順
VDS= 最大Vds/2 とする。
RL = 10K,5k,2k,1k,500,200,100,50,
.step param list RL 0K,5k,2k,1k,500,200,100,50,20,
で、
.DC 0V 5V
でDC解析し、Idsが立ち上がり始めるVth電圧、
2. AC解析による周波数特性(周波数:利得)の把握
#1で求めたVth電圧を、
.ac dec 100 1 200Meg
3. 調査したFETの特性を一覧表として作成する。(図1.)
 |
| 図1. N-MOS FET特性の調査(一例:ここでは一部データに限定) |
関連文書: